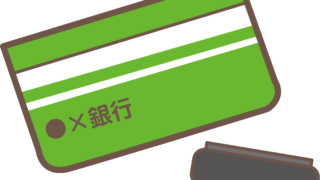父が亡くなって6年たちました。
月日がたつのは早いなと思います。
6年前、息子は中学一年生で、まだ声変わりもしていないかわいい声でした。
父にとっては最後の孫でした。
ほかの孫はすでに、成人していたので、父は特別に息子をかわいがってくれました。
父は、古びた老人病院で、最期の時を迎えました。
老人病院の実態、そこはまるで姥捨て山のようでした
父は糖尿病で、入退院を繰り返していたのですが、足を切断したのち、不本意な老人病院に転院することになりました。
急性期を過ぎた高齢者は病院に3ヶ月以上入院できないこと、ご存知でしょうか?
その理由は、3ヶ月を過ぎると病院に支払われる入院医療報酬が極端に減るという制度があるからなのです。
これは、「高齢者の長期入院」つまり3ヶ月以上高齢者を入院させていると、病院の収入が減るということで、経営が成り立たなくなる制度なのです
父は三か月ごとに、病院を転々としました。
膝から下を切断した時はとても大きな施設の整った病院でした。
そこで術後のケアを行ってくれるのは三か月までと決まっていました。
今、思うといつもいつも転院先を探していた気がします。
父は、本当は家に帰りたかったのだと思います。
でも無理でした。
片足のない父の介護を、高齢の母ができるわけがありません。
兄も妹も私も、自分の家族を守らないといけないわけで、父の希望をかなえてあげることはできませんでした。
老人ホーム、高齢者住宅、療養型病院等々、探し回りました。
片足のない父を受け入れてくれるところはなかなかみつかりませんでした。
母が、通えるところで、やっと老人病院をみつけました。
都内で、ごくまれに、ずっといてもいい老人病院があります。
父はそこに転院しました。
見学や相談に何度も行き、そこに決めたのですが、その老人病院はまるで姨捨山でした。
ただ死を待つ場所のように見えました。
看護婦さんやヘルパーさんの数も少ないです。
なぜって治療をする必要がない高齢者がほとんどだったからです。
どこの病室も、意識がなくチューブをつけてただ横たわっている高齢者がたくさんいました。
認知症専門の病室もあり、そこからはいつも喚き声が聞こえてきました。
そしてお見舞いにくる家族もほとんどいません。
ここは現代の姨捨山だと、私は思いました。
6年たった今も、その老人病院の実態を生々しく覚えています。
父は、4人部屋の一番奥の窓際に入院していました。
救いは、そこから空が見えたことです。
父はいつも空を見上げていました。
そして家に帰ることはもう無理なのだとあきらめて、日々生きる気力をなくしていったのだと思います。
そんな父の元へ、母は義務のように通い続け、母もまた壊れていきました。

自分の家の布団の上で、最期を迎えたい、そう願っている高齢者は多いと思います。
私もそうです。
最期は家で迎えたい。
でもそれはそれで難しいようです。
姨捨山のような病院へ入る前にぽっくり逝きたいなんて、思います。